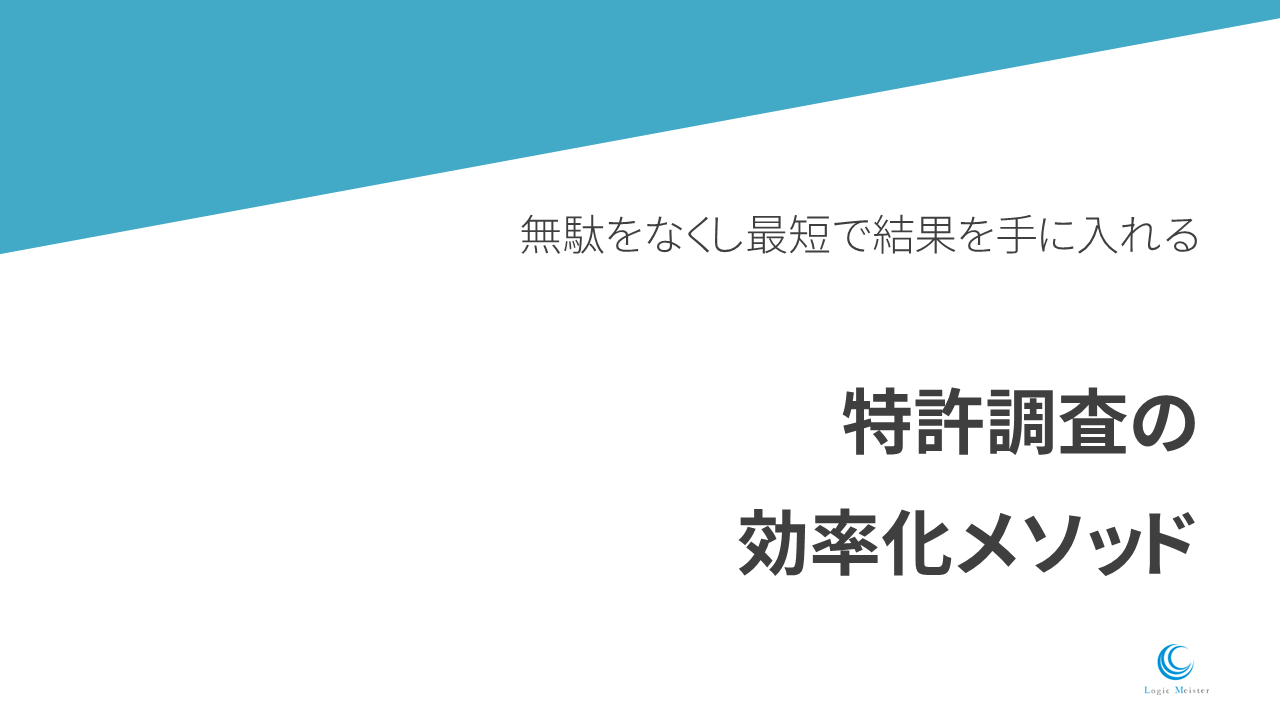ホンダ初代知的財産部長が語る、武器としての知財の使い方―『知財スペシャリストが伝授する交渉術 喧嘩の作法』【知財書籍紹介】
画像引用元: https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486310149X/wedge0541-22
今回は知的財産に関する書籍のなかから、ホンダで初代・知的財産部長を務めた久慈直登さんの著書を取り上げます。
知財戦略を指南する本というのはすでに色々なものが世に出ています。しかし、日本を代表する企業の知財戦略を指揮してきたという経験に基づいて書かれたものとなると、あまり例は多くないのではないでしょうか。
「もっと自社の知財の価値を高めたい、そのための実践的なノウハウを知りたい」とお考えの皆様、知財担当者だけでなく企業経営者の方々にもぜひご一読いただきたい本をご紹介します。
『知財スペシャリストが伝授する交渉術 喧嘩の作法』
知財は、産業競争において直接相手に行使できる唯一の武器である。知財の権利行使により、相手の企業活動自体を止めることまでできる。知財以外に、そのような強烈な制度はない。
なぜ、技術力のある日本企業が世界で勝てないのか?技術力で勝負するには何が必要なのか?参入障壁をいかに築き、いかに突破するか?事業と研究開発、知的財産をいかに連携させるか?
もはや他人事ではなく、仕事をする人ならば知っておきたい知識だが、敷居が高いと感じる人が多く、またなかなか馴染みがない。そこで、知財スペシャリストの著者に、実例を元に知財についてわかりやすく解説してもらった。知的財産を事業競争力として活用するための経営戦略、事業戦略が詰まった1冊。(Wedge紹介ページより引用)
本書は月刊誌「Wedge」2012年10月号~2014年6月号にて連載された記事をもとに単行本化し、2015年6月に発売されました。
「喧嘩の作法」という刺激的なタイトルに目をひかれますが、実際には知財戦略全般を扱う内容となっています。
そのなかでも、「喧嘩」にあたる他社への権利行使・交渉の部分を主題として、これに勝つための出願戦略、さらにはノウハウ防衛やパテントトロールに関する考察など、著者の生々しい体験に基づいたアドバイスを提供しています。
著者・久慈直登さんのプロフィール
元本田技研工業知的財産部長
1952年岩手県久慈市生まれ。学習院大学大学院法学研究科修士課程修了後、本田技研工業株式会社に入社。本田技術研究所で開発管理に携わった後、本田技研工業の初代知的財産部長を2001年から2011年まで務めた。2011年よりIP*SEVA(日米独の技術移転ネットワーク)ASIA代表、2012年より日本知的財産協会専務理事、知財関連の5団体の理事、2014年より日本知財学会(IPAJ)副会長を務めている。
主要論文に「Propagating green technology (Les Novelles 2011に掲載の英語論文)」がある。この提案に基づき国連知的所有権機関(WIPO)が地球環境保護のため技術移転メカニズムをWIPO GREENとして2013年から公式スタート。(「著者紹介」)
久慈さんはまだホンダに知財担当者が15名程度しかいなかったころに入社し、勤めた35年間のうちの多くで知財の仕事を手がけてきました。
1980~90年代当時全盛期だったホンダのF1レースチームなどにも、知財法務として関わっていたそうです。
そして知的財産部の立ち上げとともに2001年から10年間、初代の知的財産部長としてホンダの知財戦略全体を統括する立場にありました。
知財は他社に直接行使できる唯一の武器である
そもそも、企業はなんのために知財を取得し、少なくない資金を費やしてまで知財を保有しているのでしょうか?
この基本的な問いに対して、本書は以下のように答えています。
知財は、産業競争において直接相手に行使できる唯一の武器である。知財の権利行使により、相手の企業活動自体を止めることまでできる。知財以外にそのように強烈な制度はない。(p.1)
このことを聞いてハッとなる方も多いのではないでしょうか?
確かにライバル会社との競争に勝つといっても、商売の上では「どちらの会社の商品がよりお客様に選ばれるか」という間接的な争いに過ぎません。
そのなかで知的財産権がどのような存在かを考えてみると、ライバルに直接ぶつけることができる唯一の「武器」としての性格が浮かび上がってくるわけです。
なお著者の在籍したホンダでは、創業者・本田宗一郎の「権利は金をかけてでも、裁判してでも、主張しろ」という言葉が紹介されるとおり、権利行使をすることに積極的な文化が根付いているそうです。
新興国企業と戦ううえでの知的財産の役割
本書の特徴の1つは、外国企業、とくに近年世界市場を席巻しつつある中国・韓国をはじめとする新興国企業との関係について、議論の重点が置かれていることです。
そもそも日本で知財訴訟が比較的少なかったのは、各企業の知財部門同士が交渉してトラブルとなることを未然に防ぎ、裁判に進む前の段階で解決してきたからでした。
しかし新興国企業が相手では、これまでの「20世紀的な」日本企業のやり方はもはや通用しません。
新興国の企業はほとんど黒でも商品を市場に出してくる。それは、遅れて競争に参加したために、進んだ企業の商品をギリギリのところで真似して追いつこうとするためである。他社の知財を黙って使うことはあっても、決して使用申し入れはしない。なぜなら申し入れをすれば、多額の実施料を取られる結果になるからだ。(p.100)
「言われなければ黙っていればいい、言われたら裁判にでももちこんで、時間を稼いでいるうちに商品を売りさばいてしまえばいい」…と考えている新興国企業も多いようです。
また日本企業の多くは今まで、日本国内における競争に勝つことを主眼に置き、守りを中心に考えて大量の特許出願を日本で(ある程度は米欧にも)行う、というやり方だったといいます。
しかし、それでは日本企業が開発した膨大な技術資料を世界に向けて公開・提供していることになり、そのぶん新興国企業の研究開発費を節約させる結果になってしまうのです。
そこで本書ではアジアやアフリカといった新興国を主戦場とする出願戦略や、彼らを相手とする交渉の際の心がまえといったことについてもページを割いています。
原告訴訟の経験値を高めよ
本書のなかで繰り返し指摘されているのが、原告側で訴訟を提起する経験をたくさん積むことの重要性です。
[訴訟を]一度経験すると、次の同じような案件ではずっとうまくできるようになる。それは実戦を通じて各国の知財制度や裁判の違いを理解し、各国の弁護士や裁判官の考え方の違い、マインドの違いを肌で感じ、それにより裁判の結果が予想できるようになるからである。(p.119)
新興国企業もいずれ知財の面でも力をつけ、世界中で競合に対して知財訴訟を仕掛けるケースも増えてくると筆者は予想しています。
そのときに日本企業のほうで訴訟経験が不足していれば、彼らには到底太刀打ちできません。来るべきときに備えて、今のうちから積極的に権利行使を行う必要があるというわけです。
また知財担当者のスキルだけにとどまらず、意識やモチベーションの面でも原告訴訟は効果があるといいます。
つまり、攻撃に知財を使うほうが、防御として待ち受けて知財を使うよりはるかに楽しいということである。防御だけであれば、出願の質量をいくら上げても、つまり兵器の品質を良くし数を増やしても使いこなせず、結局使わない。(p.121)
確かに原告側ならばどの特許を使うか、いつどこの国の裁判所へ提訴するかなど、自由に作戦を立てることができますが、逆に被告側はそれに振り回されざるを得ません。
さらには攻撃側の立場で考えることで、知財を本当に「使える」権利にするためにどのような出願をすべきか、といったノウハウも蓄積されるでしょう。
おわりに
アメリカや欧米から中南米・アフリカまで、世界中のマーケットで知財を武器に戦ってきた筆者の経験から編み出された知恵が、書籍の形で読めるのは貴重なことだと思います。
ぜひ一度、手にとってみてください!
※『知財スペシャリストが伝授する交渉術 喧嘩の作法』(Amazonページに飛びます)